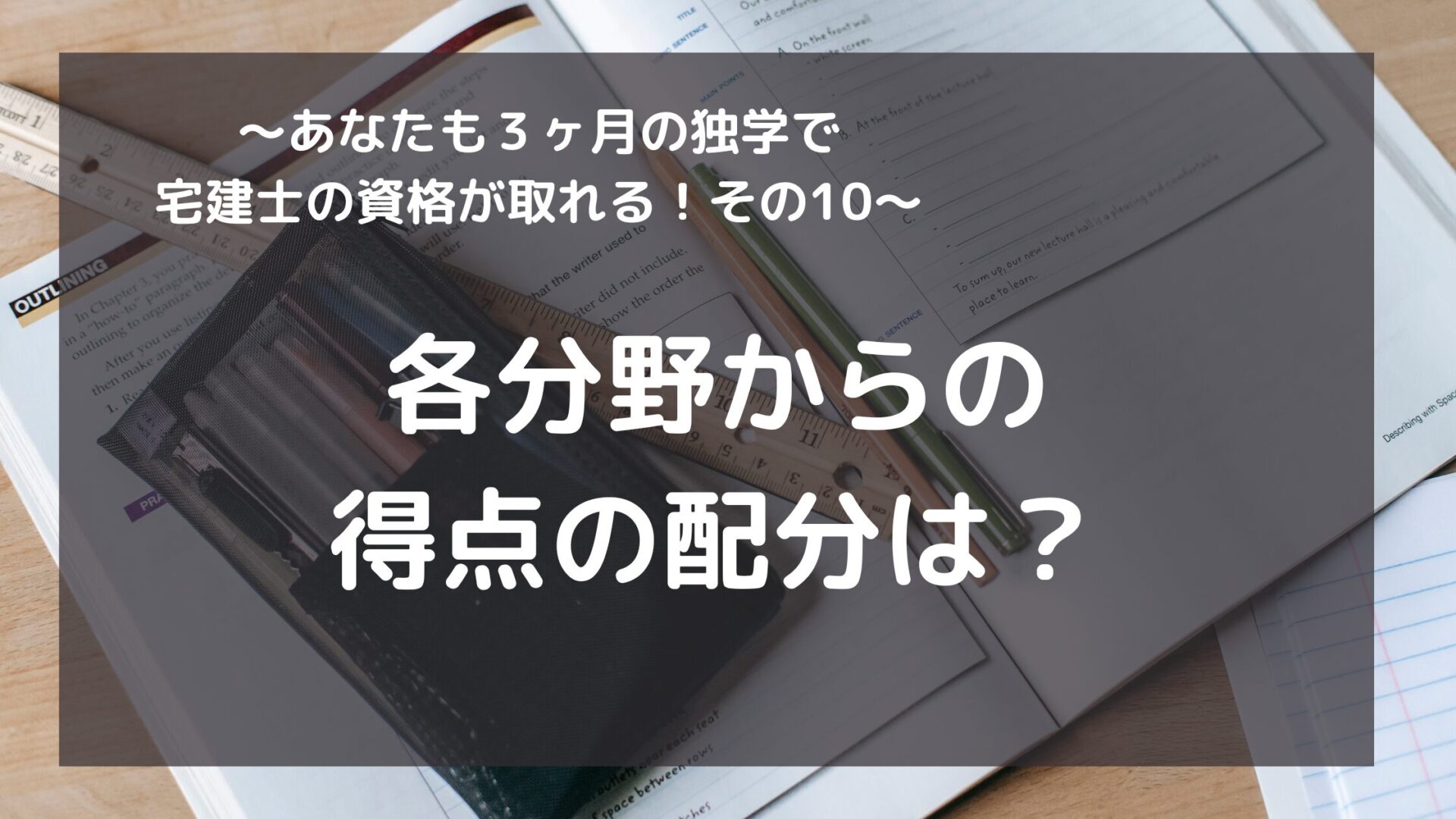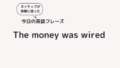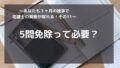各科目の目標点を決めよう
まずは私の合格点36点をどの科目からとったか参考までに。
| 科目 | 出題数 | 私の正答数 |
| 権利関係 | 14 | 9 |
| 法令上の制限 | 8 | 5 |
| 宅建業法 | 20 | 16 |
| 税その他 | 3 | 1 |
| 免除科目 | 5 | 5 |
税その他の中46問目から50問目は免除科目としています。
「宅建業法」で少なくとも18点は欲しかったけど残念ながら16点。
「法令上の制限」で7点を目指しましたが5点
また、自信があった「税その他」(5問免除除く)が1点しか取れませんでした。
代わりにあまり自信がなかった「権利関係」が9点とれ、
なんとか36点になりました。

しかしここ最近の合格基準点は36点前後
令和2年の合格ラインは38点だって!
最近の傾向を考えると38点とって余裕が欲しいところですね
宅建業法は18得点を目指そう

宅建業法は最重要科目!出題数も20問と多いけど
内容的にもやさしいものが多いから得点源だよ。
過去問を繰り返しやりこもう
満点が狙えると言われる「宅建業法」です。
私は16点とちょっと目標に届きませんでした。
アプリでもかなりやり込んだつもりだったのですがやはり本番は違いますね。
「法令上の制限」と「権利関係」どちらをとる?
短期間でとるためには「法令上の制限」と「権利関係」の勉強時間をどちらかに重点を置いた方が良いと思います。

法令上の制限と権利関係、どちらが向いてるかな?
私の場合。
民法を勉強したことがある人は「権利関係」が良いときいて、経験のない私は単純に「法令上の制限」を得点源としようと決め、勉強時間を多く取りました。
にもかかわらず蓋を開けると「権利関係」で得点が多かったんです。
「権利関係」の正答率は64%。「法令上の制限」は62%。
重点的に時間を取ったのにもかかわらず、です。
振り返ってみると、TACのテキストが私に合っていたのだと思います。
民法の具体的なトラブル等の例がイラストで説明されていたのでイメージしやすかったです。
独特な用語や細かいところの違いを覚えることが多い「法令上の制限」は私には向いていなかったのでしょう。
なぜそういう制限がかかるのか(建蔽率とか)、用途地域とか(同じような名称多い!)解答を見直しても深いところまで知識が定着していなかったため正解できませんでした。
どっちが向いているのかは人によるので、ざっとテキスト一周してから決めた方が良いと思います。
そして決めたらその分野の80%は取るように頑張ってみてください。
「税その他」の分野は得点源。2問は取ろう!
税その他(5問免除は除いてます)は3問中1問しか正解できず・・・撃沈です。
これに関しては運もあったかなと今は思います。
何せ時間が無いので最後の追い込み時期でしかしてませんでした。
とはいえここはおそらく得点が取りやすい分野です。
試験前には満点取れる自信があったのも事実です。
今思えば根拠のない自信です笑
まとめ
その年によって合格点が変動する宅建試験ですがここ10年は35点前後で変動しているようです。
(令和6年度は37点)
私は受けた令和元年のテキストには少なくとも37点を取ろうと書かれていましたが、最近の傾向だとプラス1、2点は上がって来ているようです。
それでも人気のある資格ですので今後も受験する人は多いでしょう。
時間がない中でも最低限の勉強時間で絶対合格できます。
頑張ってください